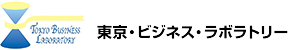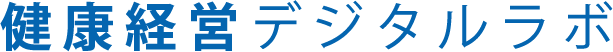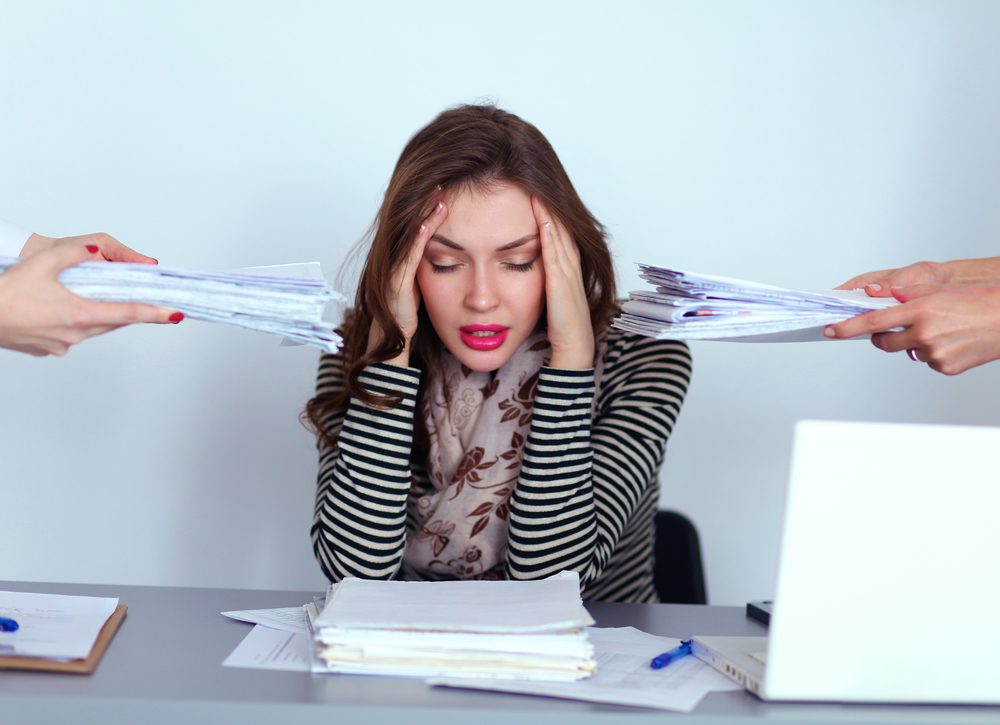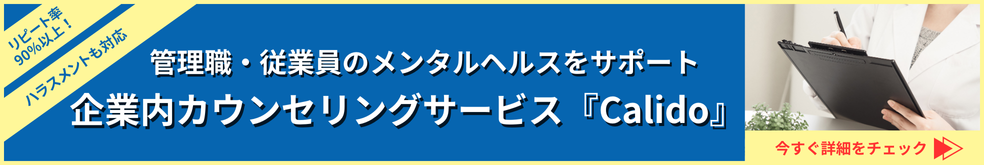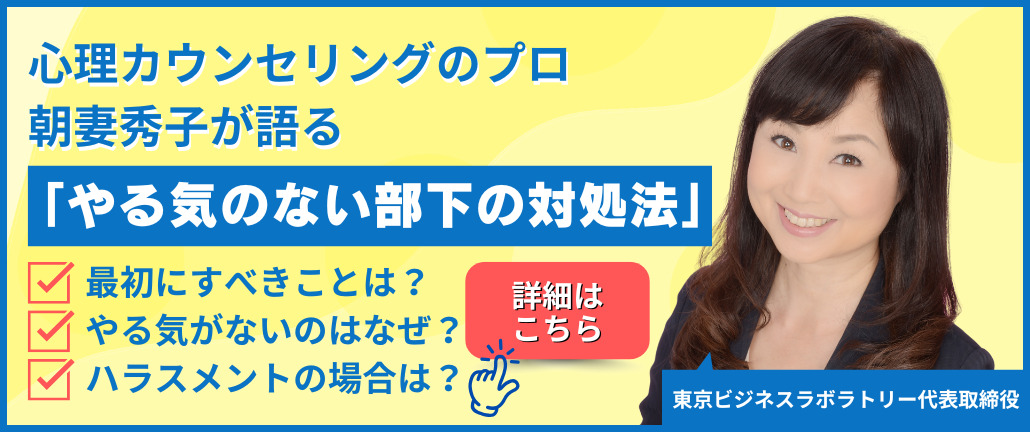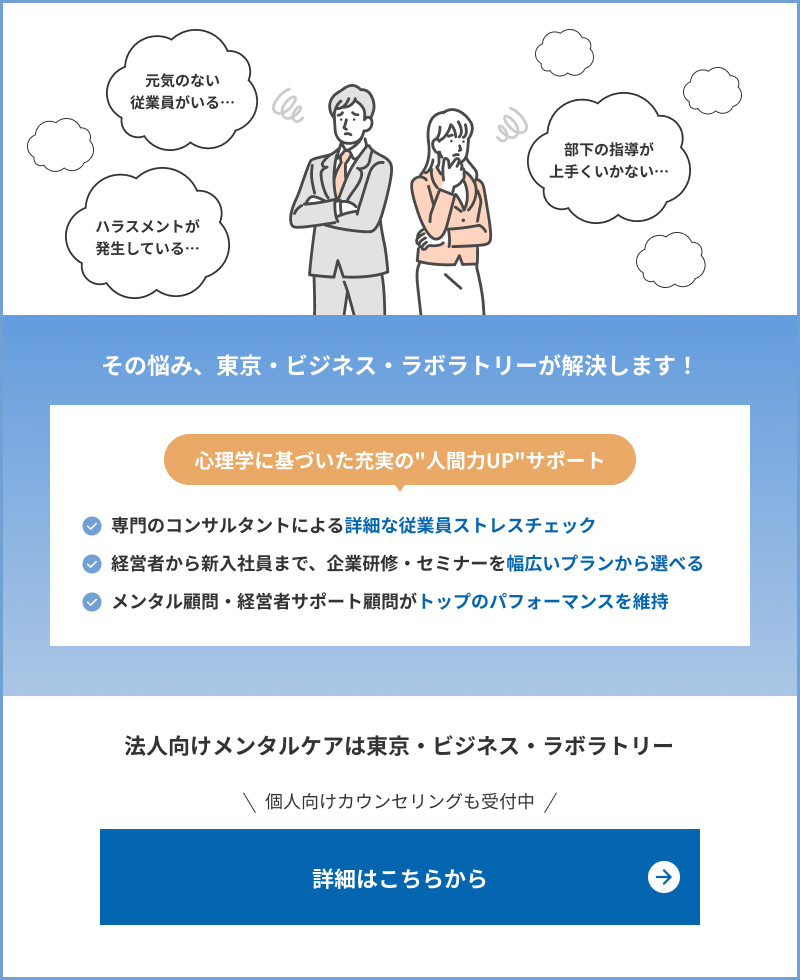目次
休職とは
「休職」とは、さまざまな事情で就労が困難な社員を、一時的に休ませる制度です。利用すれば会社との雇用関係を維持したまま、一定期間仕事を休むことができるため、社員にとっては非常に助かる制度だといえるでしょう。
休職制度は、法律で会社側に義務付けられている制度ではありません。社員が仕事を長期間休んでしまうと労働力が減り、生産性が低下するリスクがあるため、あえて休職制度を導入しないという会社もあるでしょう。
ですが、社員の健康を守ることは、会社が果たすべき義務のひとつです。とくに近年は心の健康、すなわちメンタルヘルス不調から社員を守る必要性が重要視されており、社会的責任を考慮して、休職制度を設ける企業が増えています。
メンタルヘルス対策として休職制度を設けるメリット

メンタルヘルス対策として休職制度を設けるメリットを紹介します。自社に休職制度を設ける際の参考にしてください。
離職率の低下
休職制度があれば、メンタルヘルス不調で従業員の就業が難しい状態になったとき、すぐに解雇ということにはなりません。そのため、離職率を抑えられます。
休職という選択肢は、福利厚生の充実にも直結しており、多様な働き方や、安心できる職場環境を求める人材の確保に役立つことも期待できます。
休職者以外の従業員にとっても、安心できる職場としてエンゲージメントが高まるでしょう。働きやすい雰囲気の職場をつくる上で、休職制度の導入は役立ちます。
復帰後の生産性向上
休職の選択肢がない場合、従業員は無理をして勤務するか、退職するかの2択しかありません。
無理をして仕事をすると、パフォーマンスが低下するおそれがあります。退職すると貴重な戦力を失ってしまいます。どちらの選択肢も、企業にとってはデメリットしかありません。
一定期間でも休職をして万全の状態で復帰してもらえれば、将来的には従業員本人の生産性の向上が期待できるでしょう。会社全体の生産性を高めるためにも、休職制度の導入は効果的です。
企業イメージの向上
休職は法律上で定められているわけではなく、制度として必ず設定しなければならないものではありません。しかし、休職制度を設けておけば外部から「社員を大切にしている会社」として評価され、企業のブランド価値の向上につながります。
企業のイメージアップは、商品の売上増加や新規顧客の獲得、さらには競合他社との差別化などに影響します。従業員を守るためだけでなく、企業全体の評価を高める上でも、休職制度は役立つでしょう。
メンタルヘルス対策として休職制度を設けるデメリット

休職制度には離職率の低下や、生産性の向上などのメリットがある一方で、デメリットもあります。休職制度を設ける際は、メリットとデメリットを比較して、慎重に検討しましょう。
休職期間中の社会保険料の負担
休職期間中は休業とは異なり、給与の支払いの必要がありません。しかし、雇用契約が解消されるわけではないため、社会保険料を企業と従業員の双方が折半して払う必要があります。
支払う必要がある社会保険料は、健康保険料や厚生年金保険料、介護保険料などです。これらの社会保険料の支払いが従業員にとって負担となるかもしれません。
従業員に対して、休職中も社会保険料が発生することを事前に説明しておくことが大切です。休職している従業員との間で、金銭面のトラブルが発生しないように注意しましょう。
人事担当者の業務ひっ迫
心身の不調を理由にした従業員の休職手続きは、その過程が秘密裏に進められるケースが多くあります。そのため人事担当者は、従業員が休職することが漏えいしないように注意しながら手続きを進めなければならないというプレッシャーがかかりがちです。
従業員の休職前から休職中、復帰後にかけて細かい気配りや支援も必要になります。人事担当者に業務が集中しすぎないように、部署や会社全体でフォローをすることが大切です。
他の従業員の業務増加
従業員が休職をした場合、残された従業員で仕事を分担する必要があります。業務量が増えると負担もかかり、ストレスや疲労を感じる社員が出てくるかもしれません。
残された従業員の負担を軽減しようとして、従業員を補充する方法もあります。しかし、休職は復帰を前提にした制度であるため、新規雇用によって従業員が過剰になる可能性もあります。
従業員が休職することによる残された従業員の業務増加は避けられません。従業員が休職した場合は、残された従業員に対して真摯に説明をし、業務量の増加について理解を求めることが大切です。
万が一、休職した従業員が復帰できなかった場合は、早期に人材を確保しましょう。休職した従業員が万全の状態で復帰できるとは限らないため、万が一を考えて早めに採用活動を始めておくことが大切です。
メンタルヘルスの不調による休職前に行っておくべき準備
社員が休職する前に行っておくべき、会社の対応を紹介します。
休職制度は法律に義務付けられた制度ではないため、会社が独自に運用方法を定めても問題ありません。社員のメンタル不調には早期に対応する必要があるため、日頃から会社が行うべき次の2つのポイントを理解して、準備をしておくことをおすすめします。
休職が必要かどうか判断する
会社は、社員が仕事を休む必要があるかどうかを、常に判断する必要があります。当然ながら、職場や仕事が原因でメンタル不調になった社員を、会社側から一方的に解雇することはできません。
安全配慮義務の観点からも、休職の判断は会社にとっての義務です。社員の普段の様子や勤務状況、休暇申請の様子などを確認して、仕事を休ませるべきかを判断しましょう。上司が面談を行うのも効果的です。
定期的なストレスチェックも実施しましょう。厚生労働省による、「職業性ストレス簡易調査票」を活用してください。職場環境や、直近一か月の心理状況についてなどの質問事項がまとめてあり、社員が抱えるストレスの状態を把握するのに役立ちます。
ストレスチェックを行ったら、会社が調査結果を適切に管理する必要があります。調査結果には社員の個人情報やプライバシーに関する情報が多く含まれているため、休職の判断のために社内で共有する場合にも、必要最小限の範囲にとどめましょう。
また、会社として、メンタル不調になった社員が傷病手当金を受給できるかどうかの判断もする必要があります。
休職する社員との間で取り決めをしておくべきこと
社員が休職する前に、会社が休職期間内に関する取り決めをしておくことが大切です。取り決めをしておくことで社員は安心し、仕事を休んで回復に集中できるでしょう。
まず、休職中の社員と会社との連絡方法を決めてください。メンタルヘルス不調で休職すると、孤独感や将来に対する不安を抱えてしまう方が多いため、相談体制を整えておくことをおすすめします。
また経済的な不安を減らすために、休職中の給与の取り扱いも決めておきましょう。利用できる公的サービスなどについても、会社側から説明できれば丁寧です。
あらかじめ休職制度のルールや復職支援について説明し、社員の理解を得ておくことも重要です。復職までの手続きについても説明して、不安の軽減に努めましょう。
メンタルヘルスの不調による休職中の注意点
社員がメンタルヘルス不調で休職している際に、企業が行うべき対応を紹介します。
休職はあくまでも一時的な措置です。将来的に職場に復帰することを見据えて、社員が安心して会社に戻れる配慮をしてください。
定期的に連絡を取る
会社は、休職中の社員と定期的に連絡を取りあう必要があります。休職期間内でも、社員の健康状態や回復状況を把握しておくのは、雇用する会社の義務と考えてください。
休職前の取り決めに従って、休職中の社員から定期的な報告を求めましょう。連絡を取り合うことで、社員が休職中に抱えている孤独感や疎外感を会社が把握しやすくなり、早期に対処するのに役立ちます。
休職中の各種手続きを円滑に行うためには、最低でも1か月に1度、可能であれば月に2回程度は連絡を取り合うことが無難です。回復状況の確認にあわせて、無理のない範囲で復帰の意思の確認もしてください。
休職中に自宅外いる様子が確認された場合には
休職中の社員が自宅外にいる様子が確認された場合には、会社として適切に対処する必要があります。
とはいえ、休職中だからといって、会社が社員の外出を制限することはできません。生活圏内なら、通院や買い物などで外出するのは当然です。
メンタルヘルスの不調では、外出もリハビリの一部としても認められるのが一般的です。実家に帰省することは、ゆっくりと心身の疲れを癒すためにも役立つでしょう。
ただし、観光目的の長期旅行や海外旅行などは考えものです。休職中の社員が、心身ともに健康でないとできない活動をしている場合は、会社として事情を聞きましょう。
また休職中の社員のSNS発信は、控えるよう指導してください。ほかの社員がSNSを見たときにネガティブな感情をもち、職場復帰したときの環境が悪くなるリスクがあるため、事前に社員に注意しておきましょう。
メンタルヘルスの不調による復職時にはどのような対応が必要か
最後に、メンタルヘルス不調の社員が休職から復職する際の対処法を紹介します。
メンタル不調は、繰り返す傾向があります。苦労して復職しても、すぐに体調を崩してしまうのでは本末転倒なので、会社としてしっかり対処してください。
復職できるかどうかの判断
休職中の社員から復職の希望があった場合は、本人と主治医だけでなく、上司や人事担当者、産業医の意見も聞きながら判断することが大切です。会社として、社員が職場で仕事ができるまで回復しているかを、十分に確認してください。
メンタルヘルス不調の場合は、調子が良い日と悪い日で波があることが多いです。波の揺れ幅がなく、安定していることが復職の条件だと考えましょう。
心身の不調が回復しても、本調子ですぐに働き出せるわけではありません。とくに原因が職場にある場合は、以前と同じ状態で働くとさまざまな支障がでるため、本人の希望も聞きながら、短時間勤務や部署変更をすることを検討してください。
再発防止の対策
復職後のメンタル不調を防ぐためにも、再発防止対策が必要です。復職後は定期的な面談やストレスチェックを行うことで、再発の早期把握に努めましょう。
東京・ビジネス・ラボラトリー(TBL)のストレスチェックを活用すれば、休職後の社員のケアは万全です。プロによる相談窓口や心理学を用いた丁寧な個別カウンセリングは、復職後の不調の再発を防ぐのに効果的です。
企業向けの研修やセミナーなどを開催しているのも、東京・ビジネス・ラボラトリーの魅力でしょう。心のケアから社員の復職支援だけでなく、コミュニケーションスキルや教育スキル、組織力の向上など、幅広いニーズにあわせた企業サポートが実現します。
東京・ビジネス・ラボラトリー(TBL)は、企業のメンタルヘルス対策のノウハウの蓄積にも貢献します。社員のメンタルヘルス対策や休職からの復職支援に悩んだら、ぜひお気軽に東京・ビジネス・ラボラトリーにご相談ください。
まとめ
メンタルヘルス不調は、個人の責任ではありません。会社には社員の心身の健康を守る義務があるため、日頃から的確に状況を把握し、休職制度を活用しながら早期回復を促しましょう。
社員のメンタルヘルス対策には、ストレスチェックが効果的です。東京・ビジネス・ラボラトリー(TBL)の便利なサービスも活用して、社員のケアを心がけてください。